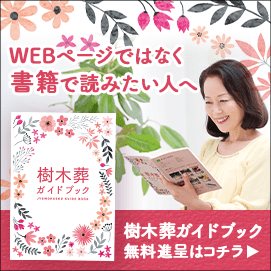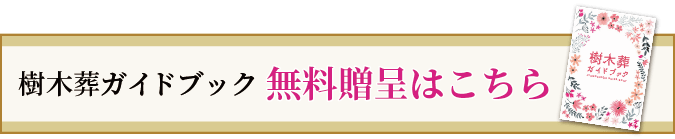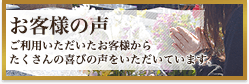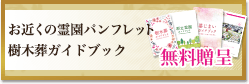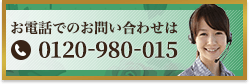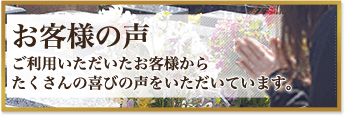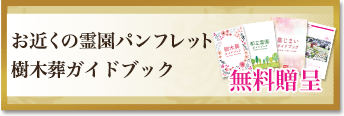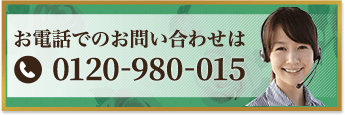未来のお墓研究所
お彼岸のお墓参りはいつ行くの?お彼岸の意味や、お彼岸にすることを解説
目次
1.お彼岸の意味と由来

お彼岸の時期には先祖供養を行うことが習慣となっています。まずは、お彼岸がどのような意味や由来を持つかを見ていきましょう。
お彼岸の言葉の意味は「極楽浄土の世界」
「彼岸」という言葉は、私たちが生きている「此岸(この世)」に対して「向こう岸(極楽浄土)」を意味しています。お彼岸には太陽が真東から登り、浄土のある真西に沈んでいくため、浄土にもっとも通じやすい時期と考えられています、
また、昼夜がほぼ同じ長さであることからも、浄土への距離がもっとも近づき、想いが通じやすくなると考えられました。よって、お彼岸に極楽浄土に向かって拝むと功徳があると信じられ、「仏教修行を行う期間」と捉えられるようになったのです。
お彼岸は日本独自の仏教的習慣
実は、お彼岸は日本独自の仏教的習慣であり、ほかの仏教諸国ではこの時期に先祖供養を行うことはありません。日本のお彼岸の起源は諸説ありますが、承和7年(840年)に記された『日本後紀』に、ある僧侶が春秋2回法要を行っていたという記録が最古といわれています。つまり、お彼岸の法要は平安時代から続く日本の慣習なのです。
2. お彼岸の時期

お彼岸は、春のお彼岸と秋のお彼岸の年2回あります。3月の春分の日、9月の秋分の日を中日とした前後3日間を指し、初日を「彼岸入り」最終日を「彼岸明け」と呼びます。
春彼岸と秋彼岸の正確な日付は、国立天文台が地球の運行状況を観測し、前年の2月1日に発表します。国立天文台のホームページでは、地球の運行状態が変わらない前提で2030年までの春分の日・秋分の日を発表しています。そちらをお彼岸の目安とすることはできますが、正確な期間は毎年のカレンダー等で確認しましょう。
春のお彼岸は「春分の日」前後
春彼岸は、春分の日を中心とした前後3日を含めた7日間です。
| 彼岸入り | 春分の日 | 彼岸明け | |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 3/18(土) | 3/21(火) | 3/24(金) |
| 2024年 | 3/17(日) | 3/20(水) | 3/23(土) |
| 2025年 | 3/17(月) | 3/20(木) | 3/23(日) |
秋のお彼岸は「秋分の日」前後
秋彼岸は、秋分の日を中心とした前後3日を含めた7日間です。
| 彼岸入り | 秋分の日 | 彼岸明け | |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9/20(水) | 9/23(土) | 9/26(火) |
| 2024年 | 9/19(木) | 9/22(日) | 9/25(水) |
| 2025年 | 9/20(土) | 9/23(火) | 9/26(金) |
3. お彼岸にやること

春も秋も、お彼岸ですることは基本的に一緒です。お墓参りをはじめとしたご先祖さまへの供養を行い、感謝を捧げる期間としましょう。
お墓参り・お墓の掃除
お彼岸ではお墓参りをおこなうのが一般的です。普段、お墓の掃除が十分にできていない方は、お彼岸のお墓参りでしっかり掃除するとよいでしょう。雑草を取り除き、墓石を水洗いするだけでも十分に綺麗になります。掃除の時間が取れない方は、墓石専門のクリーニング会社に依頼するのもひとつです。
仏壇・仏具の掃除
彼岸は、節目として仏壇や仏具を綺麗にするよい機会でもあります。普段は手の回らない自宅の仏壇、仏具をていねいに掃除しましょう。掃除する際に仏壇を傷つけないように、仏壇の種類に合わせた掃除の方法を確認しておいてください。
お花・お供物
お彼岸中、自宅の仏壇やお墓にはお花とお供物を用意します。他家の法要に参加する場合は、手土産としてお供物を持参しましょう。進物線香や菓子折りなど日持ちする消えものが定番ですが、デパートなどで販売している果物の籠盛や、香典をお包みする場合もあります。身近な方に相談しておくとよいでしょう。
お彼岸におすすめのお花
この時期にはお花屋さんにお彼岸用の花が用意されています。事前にアレンジメントを依頼しておくとスムーズです。春のお彼岸には、スイートピー・トルコキキョウ・カーネーション・アイリスなど、淡く優しい色合いの花がおすすめです。秋のお彼岸には、リンドウ・菊・ケイトウなど、落ち着いた品格のある花がよいでしょう。
お彼岸におすすめのお供物
春のお彼岸には「ぼた餅」、秋のお彼岸には「おはぎ」がお供物の定番です。「ぼた餅」「おはぎ」は、名前の由来となった花が「ぼたん」「萩」と違うだけで、今では同一のお菓子と捉えることが多いようです。そのほか、故人が好きだった食べ物やお酒、果物・菓子折り・お花・線香・ろうそくも定番です。お供物を置く場所や置く期間を考えて選びましょう。
彼岸法要(彼岸会)
寺院や霊園によっては、お彼岸の時期に彼岸法要(彼岸会)を行うことがあります。彼岸法要は、お寺の檀家やお墓を持っている人が参加できる合同法要です。服装は喪服ではなく、黒やグレーなどの落ち着いた平服で問題ありません。
彼岸法要でお布施を持っていく場合、相場は3,000円~10,000円程度です。霊園によっては金額が決められていることもありますので、確認してから参加しましょう。
4. お彼岸におすすめの料理
ご先祖さまへの感謝の気持ちを込めて、お彼岸には普段とは違った料理をしてみるのもよいでしょう。ここでは、定番のおはぎと精進料理についてご紹介します。
おはぎ(ぼた餅)

おはぎは和菓子屋さんやスーパーなどでも買えますが、作り方は意外に簡単です。家族と一緒に作ってみても楽しいでしょう。今回は、市販のあんを使ったおはぎのレシピを紹介します。
【材料】
もち米1.5合
うるち米(普通のお米)0.5合
水2合分
市販のあん適量
【作り方】
1.もち米とうるち米を合わせて水で洗ったら、ざるに上げて1時間置く。
2.炊飯器に合わせた米と水を入れて炊く。
3.炊き上がったら、先を水でぬらしたすりこぎで潰す。
4.手水をつけ、潰したもち米を一口大の俵型に成形する。
5.ラップの上にあんを塗り広げ、成形したもち米を中心に置く。
6.ラップを使ってもち米をあんで包んだらでき上がり。
精進料理

お彼岸はご先祖さまの供養をするとともに、仏様の世界に達するための修行期間とされています。そのため、この期間には精進料理をお供えし、自分たちも食べるようにしましょう。
基本的なルールを守れば、故人の好きだった食材や旬の食材を中心にメニューを考えても問題ありません。お彼岸を機に、日本人が古くから親しんできた精進料理に触れてみるのもおすすめです。
基本的なルールを守れば、故人の好きだった食材や旬の食材を中心にメニューを考えても問題ありません。お彼岸を機に、日本人が古くから親しんできた精進料理に触れてみるのもおすすめです。
5. お彼岸とお盆の違い

春と秋に行われるお彼岸と、夏に行われるお盆の違いについて解説します。お彼岸は現世と極楽浄土がもっとも近づく日で、あの世に想いが通じやすくなる日と考えられています。これに対してお盆は、仏教用語の「盂蘭盆会」と儒教思想が混ざり合い生まれた独特の習俗です。お盆にはご先祖さまの魂が現世に帰ってくるとされ、ナスやキュウリで作った「精霊馬」を飾って迎え入れる準備をするのが一般的です。
「あの世に想いを馳せるお彼岸」と「ご先祖さまを迎え入れて、送り出すお盆」では、大きく意味合いが異なります。しかし、お彼岸とお盆はともにご先祖さまの魂を身近に感じられる行事ですので、お墓参りに適した時期といえるでしょう。
5. 意味や由来を知り、有意義なお彼岸のお参りを

お彼岸はほかの仏教諸国にはない日本独自の仏教習慣です。かつ、平安時代から執り行われている歴史ある行事でもあります。お彼岸に7日間という長い期間が設けられているのは、日々の生活がどれだけ忙しくても、7日間あればご先祖さまに想いを馳せることができるという意味合いも含んでいるのです。
普段、「お墓が自宅から遠い場所にある」「忙しくてお参りに行けない」という方は、お彼岸という機会にお墓参りをしてご先祖さまに感謝を伝えてはいかがでしょうか。