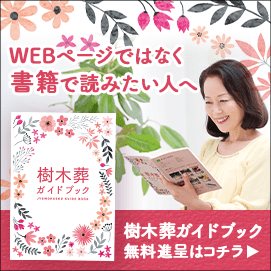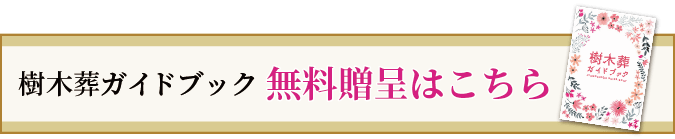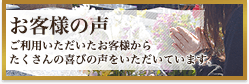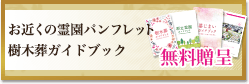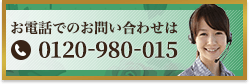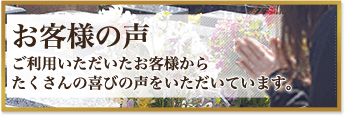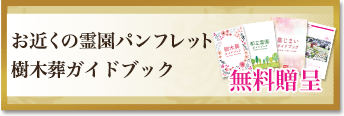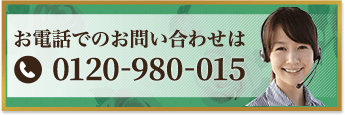未来のお墓研究所
【納骨堂とは】納骨堂の種類や永代供養との違い、メリット・デメリットを解説

目次
納骨堂とは

まず、納骨堂の定義と特徴、「永代供養」との違いを確認しましょう。
納骨堂の定義と特徴
納骨堂とは、個人や家族の遺骨を納めるスペースを備えた建物のこと。一般墓や樹木葬と並ぶお墓の1種です。もともと納骨堂は、遺骨をお墓に埋葬するまでの期間、一時的に骨壷を預ける(預骨)のための施設でした。しかし、お墓の代わりとして利用したいというニーズが増えた背景から、近年はお墓として認知されるようになったのです。昔ながらの一般墓を「一戸建て」にたとえた場合、納骨堂を「マンション」と考えるとイメージしやすいでしょう。
永代供養との違い
納骨堂と永代供養が混同されることがあります。納骨堂は「施設」を指しますが、永代供養は遺族に代わって霊園や寺院が遺骨を管理・供養してくれる「仕組み」を指します。最近は、永代供養が付いている納骨堂が増えていますが、必ずしも納骨堂=永代供養ではない点には注意が必要です。永代供養を希望する場合は、納骨堂のほか、樹木葬や合祀墓・集合墓なども選択肢に入るでしょう。
納骨堂の種類

納骨堂は骨壷の収蔵方法などでいくつかのタイプに分かれています。ここでは、6つのタイプの納骨堂をご紹介します。
ロッカー型の納骨堂
コインロッカーのように並んだ棚に骨壷を納めるタイプの納骨堂です。かつては、見た目が味気ないため敬遠されることもありました。しかし、近年は趣向を凝らしたデザインのものや、遺族がお参りしやすいようロッカーの中に小さなお仏壇を設けたものもあり、ロッカー型の人気が高まっています。1つひとつのスペースは小さいものの、完全に個別のスペースで供養できることがロッカー型のメリットです。
仏壇型の納骨堂
仏壇型はまさしく仏壇が横並びになった納骨堂のことで、霊廟型とも呼ばれます。家庭にある仏壇と同様、納骨堂の仏壇も上段と下段で構造が分かれており、上段は位牌や遺影を置いたりお花を飾ったりして参拝するためのスペース。下段は遺骨を安置するスペースになっています。ロッカー型と違って1列すべてが1家庭分となるため気兼ねが不要であり、仏壇なので参拝しやすい点もメリットです。その分、費用が高い傾向にあります。
自動搬送型の納骨堂
自動搬送型は「マンション型」「ビル型」「カード式」などさまざまな俗称がありますが、建物のバックヤードに遺骨が保管されており、機械が自動的に遺骨を運んでくる納骨堂のことを指します。利用者が契約時に渡されるICカードやタッチパネルなどを操作すると、参拝ブースに位牌や骨壷が自動的に運ばれてくる仕組みです。土地不足が深刻な都市部で普及しているためアクセスしやすい点がメリットですが、その分、費用が高い傾向にあります。
位牌型の納骨堂
位牌型とは、個人スペースのシンボルとして位牌が安置されている納骨堂のことです。よく見られるのは、故人の位牌を並べた位牌棚が設けられており、それとは別の場所で遺骨がまとめて保管されているタイプ。中には、位牌と遺骨が同じ場所に置かれているタイプもあります。仏壇型と比べて個別スペースが小さくて済むため比較的安価ですが、大きさによってはロッカー型より割高になることもあります。
墓石型の納骨堂
墓石型とは、建物内に墓石を並べた納骨堂のことです。お花や線香をお供えできるので、普通のお墓に近い感覚でお参りできる魅力があります。一方で、納骨堂の管理費用とは別に墓石代がかかるため高額になる点と、お墓が不要になった際に墓じまいする必要がある点に注意が必要です。
合葬型(合祀型)の納骨堂
永代供養付きの納骨堂は一定期間を過ぎたら最終的には合祀されますが、合葬型(合祀型)を選ぶと、最初から納骨塔などに合祀されます。費用は安く抑えられますが、合祀された遺骨は二度と取り出せませんので、慎重に検討する必要があります。
納骨堂の運営主体の違い
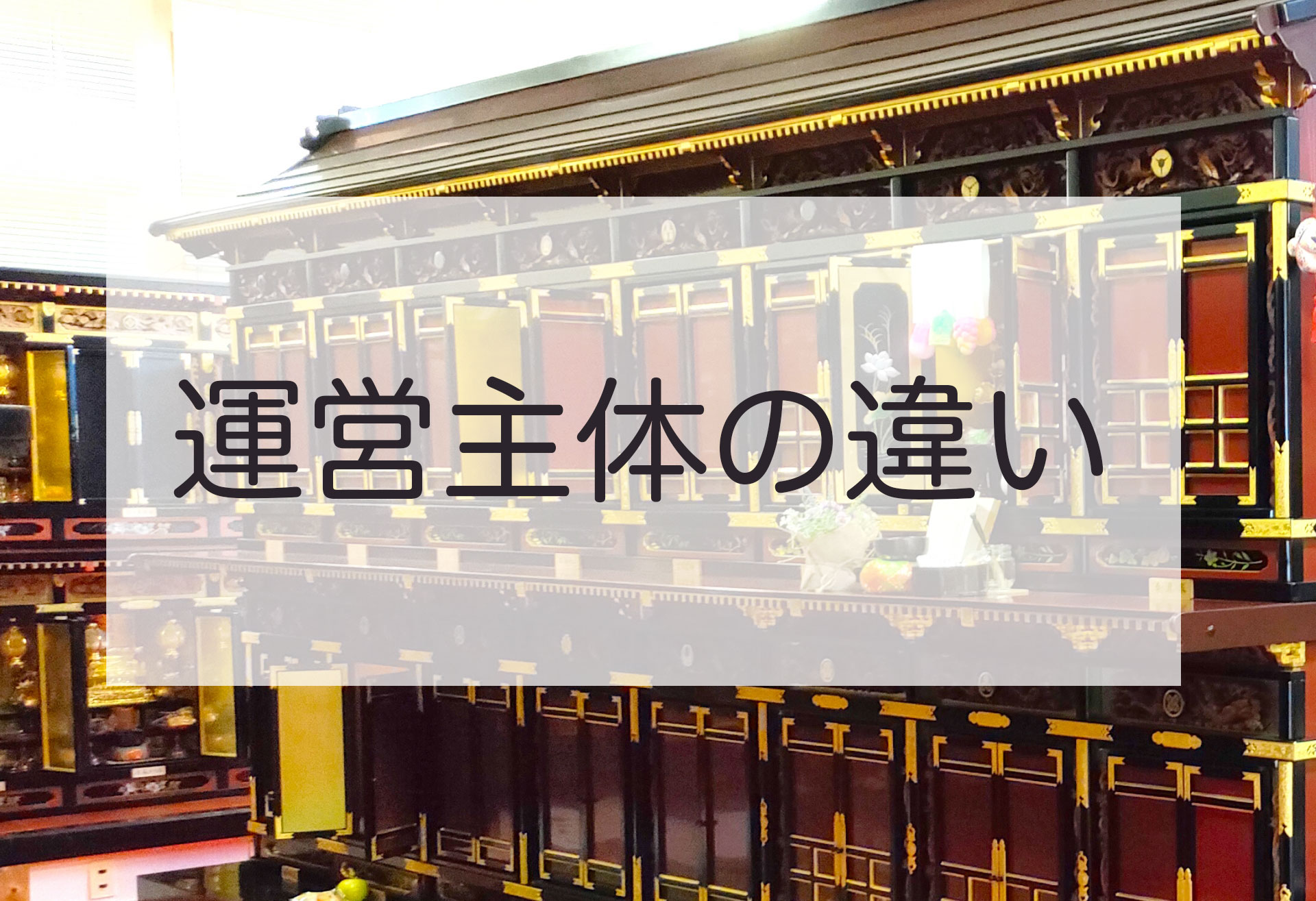
運営主体によって納骨堂の特徴が異なりますので確認しておきましょう。
寺院が運営する納骨堂
一般墓の場合、その寺院の檀家にならなければ利用できないことがほとんど。しかし、納骨堂の場合は檀家になる必要がなく、故人の宗教や信仰も問われません。お寺が管理しているため、法要をていねいに執り行ってもらえ、永代供養を安心して任せられるという点がメリットです。費用の相場は、個人用・家族用などによってかなり幅があります。
民間企業が運営する納骨堂
お寺に委託された企業や社団法人などが運営する納骨堂です。民間サービスのため設備が充実していて、サービスの質も高いという特徴があります。こちらも、故人の宗教や信仰に関わらず利用できますが、費用はやや高い傾向にあるため、事前にサービスや契約の内容をしっかり確認しましょう。
自治体が運営する納骨堂
自治体や公的機関が運営する納骨堂です。ほかの納骨堂と同様、故人の宗教に関わらず利用できますが、一定年数以上その自治体に住んでいる人でないと申し込めないケースがあるので、注意が必要です。民間の納骨堂に比べると設備やサービス面は劣りますが、その分費用は安く、倒産のリスクがないというメリットがあります。
納骨堂のメリット・デメリット
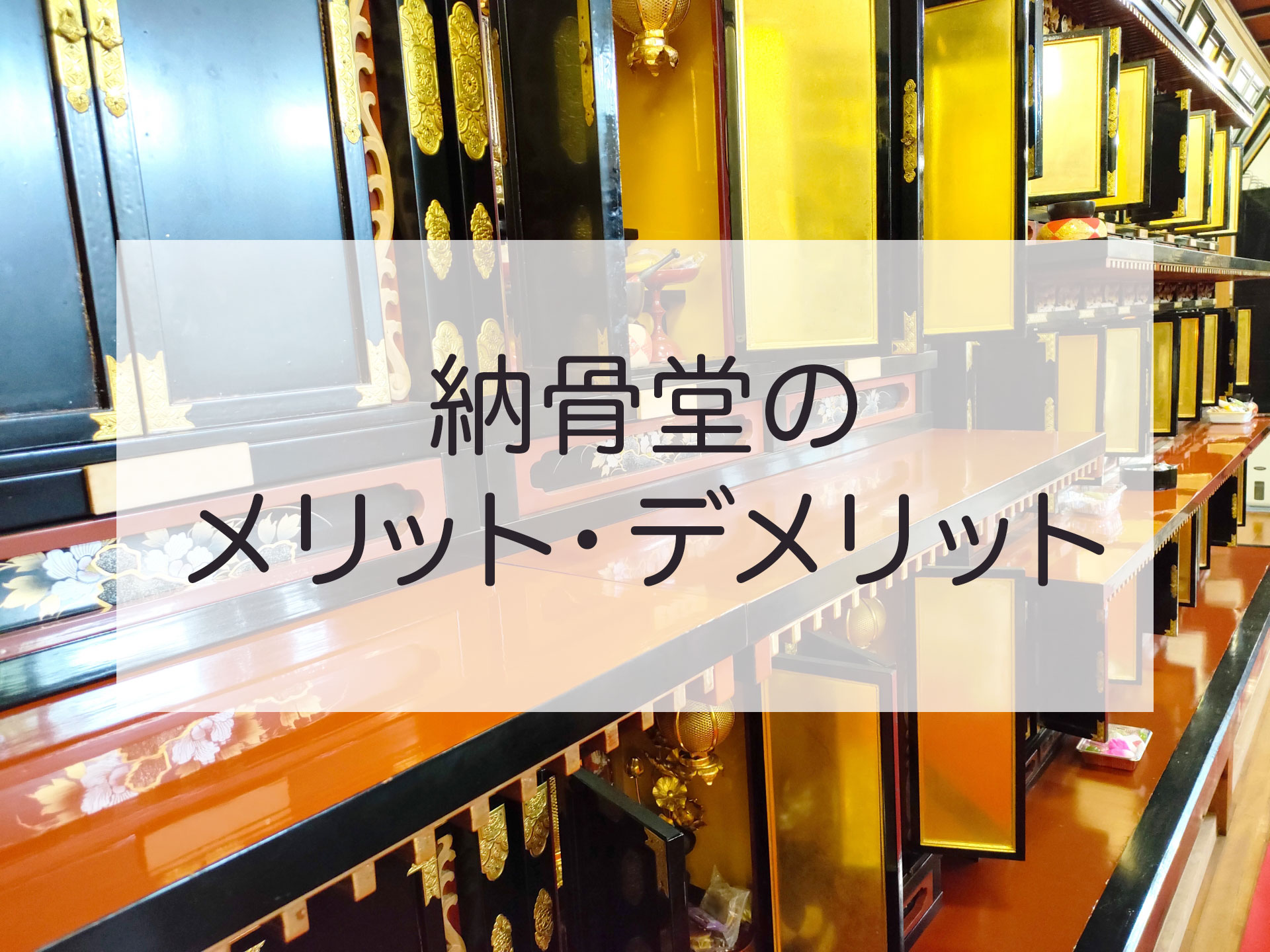
ここでは、知っておきたい納骨堂のメリット・デメリットをご紹介します。
納骨堂のメリット
一般墓に比べると、墓石を建てる必要がないため費用を安く押さえられます。また、屋内にあるため雨風で汚れる心配が少なく、掃除などの管理の手間がかかりません。都心部に多いため、アクセスしやすいこともメリットでしょう。永代供養付きであれば、お墓の相続の心配がないことも魅力といえます。
納骨堂のデメリット
施設の限られたスペースをほかの家族と共用するため、一般墓などと比べてゆっくりお参りできないという方も。お盆などお墓参りが盛んな時期には、順番待ちをしなければいけない場合もあります。建物が老朽化したり、地震などの災害で壊れてしまったりするリスクはゼロではありません。また、納骨堂に供養して一定期間が過ぎると、最終的には合祀される点は押さえておきましょう。
現地見学をして、ライフスタイルや気持ちに添った納骨堂を選びましょう。

骨壷の収蔵方式や運営主体によってさまざまなタイプにわかれる納骨堂。費用やアクセス面ももちろん大切ですが、ご先祖さまに手を合わせる場所としてご本人や家族がしっくりくるか、ということがとても重要。こればかりは、現地に足を運んで確かめてみないことにはわかりません。ぜひ、いくつかの納骨堂に見学に行き、ご自身のライフスタイルや気持ちに沿ったものを選んでくださいね。