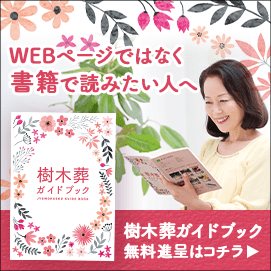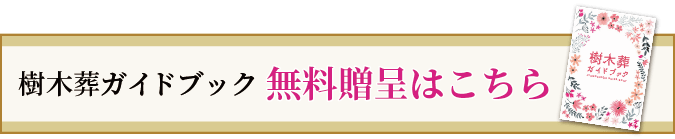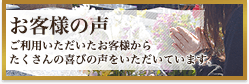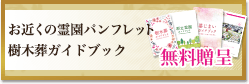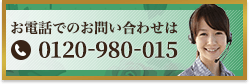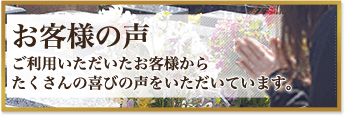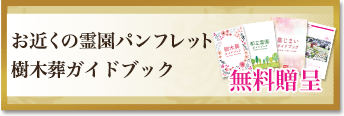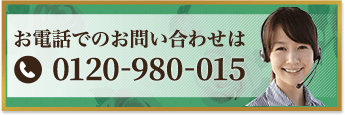未来のお墓研究所
樹木葬
お墓
樹木葬で後悔したことは?購入前の確認すべきことをご紹介

目次
1. 樹木葬とは
「葬」とつくのでお葬式の形と勘違いされる方もいらっしゃいますが、字の如く「樹木」に葬送する供養の方法です。
しかし、お墓にお骨を納める方法については、しっかりと法律がありますので、「この山のシンボル山桜の下にお骨を埋めてほしい」と希望があってもそれは叶いません。お寺さんや霊園の中にある「ここは樹木葬で納めて良い」とされているところとなります。特に形やルールの決め事はない為、様々なものがありますので自分の意思や家族の形、将来を見据えてしっかり考えることが大切です。そこで樹木葬のポイントをおさえておきましょう
2. 樹木葬の種類
おそらく皆さん、樹木葬のイメージは、「木の下に砕いたお骨を蒔く」ではないでしょうか。それも一つの形ですが、数えきれない種類があります。
ケース1
樹木をシンボルにしてその周りの地面に小さな墓石のあるもの
単に、土にまくのではなく、お墓参りを考えた時、どこに自分の家族が眠っているのかはっきりしたいという需要も多いと思います。そこでできたのが今までの竿石のしっかりしたお墓ではなく、20センチ角や直径15センチ程度の小さな石を家の区画とし樹木を中心に展開しているものです。この場合、ずっとここに入っていられるものもあれば、期限付き、例えば入ってから13年したら、合祀(他の方と一緒に祀るお墓)に移します。など形が同じでもルールが違うところも多々あります。
ケース2
シンボルとなる木の下に骨壷ごと入るもの
樹木葬となるとお骨を砕いて納めるものが主流ですが、骨壷ごと土に埋葬する、あるいはお骨袋に入れ替えてお骨を砕くことなく納めるというものもあります。こちらもケース1と同じくずっとそこに入れるところもあれば期限が来たら他に移すなどもあります。
また、「樹木葬」の中には土でも地面ではなく、花壇のような高さのあるところに木を植え付け、その周りに納めるものなど多種多様です。
3. 樹木葬の購入に向いている人とは?
では次にその樹木葬に向いている人は?ということになります。
樹木葬を選ぶ方は、自然に還りたい、もしくは好き。家族に手間が掛からない気がする。自分の後守ってくれる人に不安がある、もしくはいらっしゃらない。などの理由が多い。そうなるとそこを「満たすもの」という目線で考えることが重要です。
例えば、期限付きの樹木葬でのちに合祀になるというものでしたら、承継者がいなくても安心なので、いわゆる「おひとりさま」は良いかもしれません。また、家族がなかなかお墓参りに来れない状況という方もお寺や霊園がしっかり管理してくれるものでしたら、安心です。また自然に還りたい方なら、骨壷から出すものでないと叶いません。比較的安価であることから費用面で心配だという方にも向いている傾向にあります。しかし購入時には「確認」が必要です。
4. 樹木葬で後悔しないために確認すること
お墓選び、この場合は樹木葬にするか否かを判断するにも以下のことを確認してください。
納める形
例えば、全く結婚する様子もない40代の息子しかいないから後が心配で樹木葬にすると決めた直後に「彼女が妊娠したから結婚する」など報告があった。
もちろん嬉しいことですが、「まさか」と思ってしまうのは当然です。このように人生にはいくつものまさかがありますよね。
お墓は生きている時の延長線上にある、いわば「あの世での家」なので当然家族の形が変われば、納める方法も変わるということです。
そこで前項からお話ししている通り、骨壷のままでいざという時には別の選択肢もあるものなのか、それとも一度入ったら、もうずっとそこのみになるものなのかという確認は大事です。
ことの顛末
これは普通のお墓でも同じことが言えますが、骨壷ごと入る形のもので、例えば13年したら合祀に移します。
というルールのものだった場合、その移すときに家族がいないといけないものなのか、霊園などの管理者がその移すものもしてくれるのか。
これによって前者は将来継承者の不安のない家族で、後者は継承者の有無は問いません。また、家族が移すものだったとして、万が一にも継ぐ家族がいなくなってしまった場合はどうなるのか。
お墓は今だけでなく将来も見据えて決めるもの、何があっても不安のないように「ことの顛末」の確認を!
5.管理費の有無
なぜか樹木葬には毎年の費用は掛からないと思われている方が多いです。もちろん掛からないところもあります。
管理費とは何かと考えると清掃費用や樹木を育てる費用、またそれを守ってくれている方の人件費などです。
年に数千円のところがあります。その費用で全てをしてもらえる家族としてもおひとりの方でも安心して入れるのではないでしょうか。
これを毎年支払うところもあれば、購入時に一括で収められるところもあるので確認ください。
他にも
・選ぶときは必ず管理事務所からお参りするところまで歩く
お墓参りしやすいか、年齢を重ねても寺院内、霊園内は歩きやすい場所か
・納骨以外のサービスの有無
手続き関係もしてくれる、お葬式もこの場所でできるあるいは手配してくれるのか、仏壇の相談はできるのかなど葬送に関する他のことの確認もするとより一層安心です。
6. まとめ
今回は樹木葬のことでしたが、お骨の収納場所がお墓なのか、それが近年では納骨堂や樹木の周り、海なんてこともあります。
残念ながら自分がお墓に入るときはこの世にいませんので、自分が勝手に決めるのではなく、守ってくれる人と決めることが一番大切です。
それはおひとりの方でも同じで、核家族化の日本においては守ってくれる人が家族とは限らないからです。お墓を守りきれないと考えていた姉妹がいました。
縁はあってもあまり馴染みのない叔母が守っている墓で10年間迷っていたそうです。手続きとしては難しくないのですが叔母が大事にしている墓を安易にしまって良いのか。
という気持ちの問題です。お墓は単なる収納場所でない、私たち遺されたものにとって目に見えない大切な場ではないでしょうか。
条件だけでなくそのようなところもぜひ大切に決めてほしいと思います。

武藤 頼胡
むとうよりこ
一般社団法人終活カウンセラー協会 代表理事
主な著書に「こじらせない死に支度」(主婦と生活社)など。