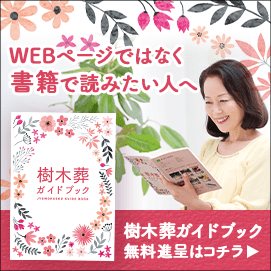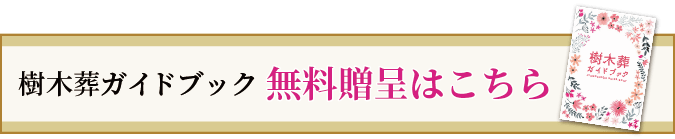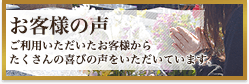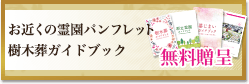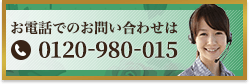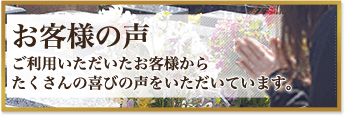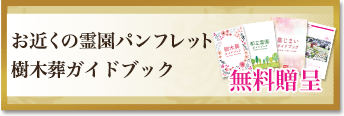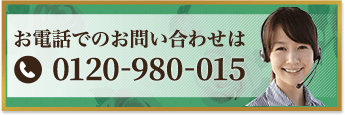未来のお墓研究所
供養
数珠の男女別の選び方を解説。宗教によって異なる持ち方も紹介

目次
数珠を持つ意味とは

お通夜やお葬式などの際に使用される数珠は「じゅず」と読み、念珠(ねんじゅ)とも呼ばれます。多くの珠(たま)を輪状に紐で繋いだ仏具で、正式には108個の珠が用いられます。
この108という数字は、仏教でいうところの煩悩の数です。珠の一つひとつが108の煩悩を司る仏様であり、もっとも徳の高い数とされています。そのため、数珠を持ち仏様に手を合わせることで煩悩が消える、徳を得られる、数珠を身につければ魔除けや厄除けになるとも言われています。
数珠は必ず持つべき?

本来、数珠は念仏の回数を数える「数取り」で使用するため、自分で読経しない場合は必須ではありません。しかし、仏式の葬儀や法事では数珠を持つことが一般的であるため、マナーとして持っておきたいものです。
数珠は、個人が持つ唯一の仏具と言われています。数珠を使うことで所有者の念が移り、所有者の分身・身代わりになるとされています。このような観点から、数珠の貸し借りは避けた方がよいでしょう。
また、数珠には多種多様な形や大きさがありますが、親玉(おやだま)・主玉(おもだま)・天玉(てんだま)・房といったパーツは共通しています。数珠の構成要素を満たさないブレスレット型のものは、数珠の代わりにはなりません。葬儀などでの使用はふさわしくないとされているため注意しましょう。
数珠の選び方

数珠には多種多様な形や大きさがあるため、どのように選べばよいのか迷うこともあります。ここでは、基本的な数珠の選び方3つをご紹介します。
本式数珠か略式数珠かで選ぶ
数珠には「本式数珠」と「略式数珠」があります。108個の珠が連なる本式数珠は正式数珠ともいい、宗派ごとに決まった形がある正式な数珠のことです。そのため、自身の宗派を確認のうえ選ぶ必要があります。本式数珠は、二重にして手にかけて使うのが一般的です。
一方、珠の数が少ない略式数珠は片手数珠ともいい、宗派を問わず使える数珠です。急なお葬式や法要などで宗派を気にせず使用できるため、最近は略式数珠を持つ人が増えています。本式数珠か略式数珠かは、自身のこだわりや使い勝手で選ぶとよいでしょう。
男性用か女性用かで選ぶ
数珠は、男性用と女性用で種類が異なります。男女兼用の数珠はなく、性別の違う数珠は使用できません。男性用の略式数珠は10~18mm程度の珠が使用されており、珠の数は22珠・20珠・18珠が一般的です。手の大きい方や存在感を出したい方は、20玉・18玉を選ぶとよいでしょう。
女性用の略式数珠も珠の数に違いはありませんが、男性用の略式数珠と比べると珠のサイズが小さく、6~8mm前後の珠が使用されています。手に馴染むサイズを選ぶとよいでしょう。
材質や色で選ぶ
珠の材質には、人口樹脂やガラス製、木製や石製などがあります。材質に決まりはないため、使用される方の好みや価格で選んで問題ありません。価格の目安は、人口樹脂やガラス製の数珠が2,000~5,000円程度、木製が2,000~20,000円程度、石製が5,000~20,000円程度となっています。
男性用は黒や茶色など渋い色が多く、女性用は柔らかく淡い色が多い特徴があります。珠や房の色は自由ですが、華美な色は避けた方が無難です。品のある落ち着いた色を選ぶとよいでしょう。
数珠の持ち方

数珠の持ち方にはマナーがあります。ここでは、多くの方が使用する略式数珠の基本の持ち方をご紹介します。
使用しない時の持ち方
式場に向かう際は、数珠を数珠入れやふくさなどに入れて運びます。着席時や移動中など数珠を使用しないときは、房を下にして左手で持ちます。仏教では、左手が仏様の世界を表すとされているため、数珠は基本的に左手で持つのがマナーです。
合掌の時の持ち方
合掌の際には、輪の中に左手の親指以外の指を通し、房を下に垂らして両手の平を合わせます。合掌した両手に輪をかける方法もあります。
焼香の時の持ち方
焼香台までは房を下にして左手に持ち、焼香台で遺族に一礼し、数珠を左手にかけたまま右手で焼香します(焼香回数は宗派により異なる)。最後に数珠を両手にかけ合掌し、遺族へ一礼をして席へ戻ります。席に戻る際も、数珠は房を下に垂らして左手に持ちましょう。
宗派ごとの数珠の違い

仏教にはいくつかの宗派があり、宗派によって数珠の持ち方に違いがあります。ここでは、浄土真宗・浄土宗・曹洞宗・臨済宗・日蓮宗の数珠の持ち方をご紹介します。
浄土真宗の数珠の持ち方
浄土真宗は親鸞(しんらん)が開いた宗派であり、西本願寺を本山とする本願寺派と、東本願寺を本山とする大谷派があります。数珠の持ち方にも違いがあることを留意しておきましょう。
本願寺派は、数珠を二重にして房を下に垂らし、合掌した両手の親指以外の指を輪に通します。大谷派は、数珠を二重にして親玉部分が上にくるように親指以外の指に通し、房は左手の甲に垂らします。
浄土宗の数珠の持ち方
浄土宗は法然上人を宗祖とし、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えればすべての者が救われるという教えの宗派です。
浄土宗の本式数珠は2つの輪を交差させた形になっており、それぞれの輪に親玉と主玉があります。合掌する際は、2つの輪を重ね合わせて両手の親指にかけ、房は親指から手前真下に向けて垂らします。
曹洞宗・臨済宗の数珠の持ち方
曹洞宗・臨済宗は禅宗とも呼ばれ、座禅を重んじた修行を行う宗派です。
曹洞宗と臨済宗の本式数珠は基本的に同じ形をしていますが、曹洞宗の数珠には金属の輪が通っています。それぞれの宗派で数珠の持ち方に違いはありません。二重にした数珠を左手の親指以外の指にかけ、房を下に垂らし、右手を合わせます。
日蓮宗の数珠の持ち方
日蓮宗は日蓮を宗祖とし、お釈迦様が説いた「妙法蓮華経(法華経)」を重要視する宗派です。
日蓮宗の本式数珠は主玉が108個ある二重タイプで、両脇のそれぞれに3本の房と2本の房がついています。数珠を8の字にねじり、右手が房2本・左手が房3本となるようにして両手の中指にかけ、そのまま手を合わせて合掌します。
数珠の扱い方の注意ポイント

数珠は、仏様と持ち主を繋ぐ大切な仏具です。バッグやポケットにそのまま入れると傷つくため、数珠入れやふくさに入れて大切に扱いましょう。
数珠を使わないときも、畳や椅子の上などに置いたままにするのはマナー違反です。席を立つときも肌見離さず持つようにしましょう。
数珠選びは直感も大切に。持ち方も理解しておきましょう

数珠は仏様と持ち主を繋ぐ仏具であり、魔除けや厄除けになるとも言われています。何度も買い替えるものではなく、長く大切に使うもの。だからこそ、数珠を選ぶ際には、数珠の種類に加え、材質や色などから感じる直感を大切にするのもおすすめです。数珠の持ち方や注意ポイントを押さえて、葬儀や法事で適切に対応できるようにしましょう。