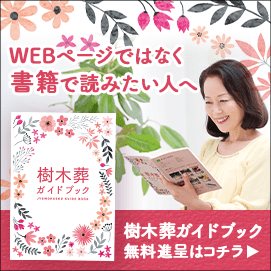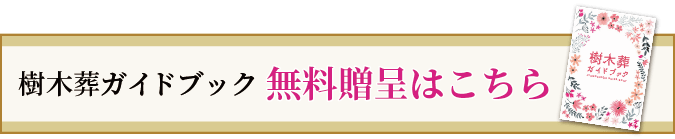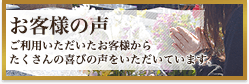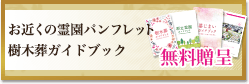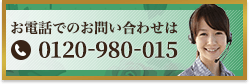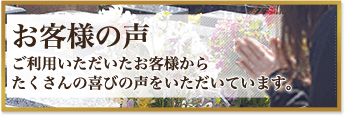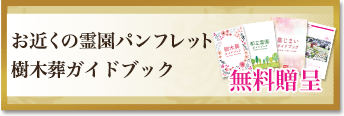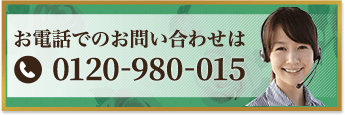未来のお墓研究所
お墓
供養
遺骨の粉骨方法と保管の際の注意点

1. 遺骨を粉骨する前にしておくこと
火葬された後の遺骨には、金属などの異物が入っていることがあります。そのため、遺骨を骨壺から取り出し、遺骨以外のものがあれば取り除きます。
また、遺骨を粉骨するためには遺骨が乾いている状態でないとできません。遺骨が湿気ていると粉骨してもペースト状になってしまい、きれいなパウダー状にならないからです。
火葬後に遺骨を骨壺に入れて保管していたものであれば、そのまま粉骨作業ができますが、もしも墓じまいなどで長い間埋葬してあった遺骨を取り出した場合は、遺骨を乾燥させる必要があります。
遺骨の乾燥方法としては3つあります。
自然乾燥
新聞紙やステンレス製のバットなどに遺骨を移し、平らにしたものを天日干しにして乾燥させます。
乾燥剤を遺骨に入れておく
密閉できる袋などに遺骨を移し、その中に乾燥剤を入れます。こまめに乾燥剤を取り換え乾燥させます。
ドライヤー
袋に入れた遺骨をドライヤーで乾かします。遺骨が飛び散らないように注意してください。
2. 粉骨するために用意する道具と粉骨方法
遺骨は2㎜以下のパウダー状にしなくてはなりません。そのため、自宅で粉骨をする場合は以下の道具を揃えておきましょう。
・手袋
・マスク
・木槌・金槌
・すり鉢もしくは乳鉢(ミル)、厚手の袋数枚
・真空パックできる袋
遺骨の部位によっては粉骨するのに力が必要なため、手袋はゴムやラバーなどの素材で滑り止め加工がされているものがおすすめです。軍手などの布製のものだと遺骨が繊維に絡まってしまうこともあるので避けた方がいいでしょう。
マスクは、粉骨の際細かい粉末が飛んでしまうため、それを吸い込まないために必ずつけて作業するようにしてください。火葬の際に思い出の品などを一緒に焼くため、体に良くない物質が混じっている可能性もあります。
木槌や金槌は、最初に大きな遺骨をある程度細かく砕くのに必要となります。細かく砕いた遺骨は、乳鉢やすり鉢に入れて2㎜以下のパウダー状にしていきます。乳鉢はサイズが小さいため何度も作業を行う必要がありますが、すり鉢なら大きめのものもあるので作業がしやすいでしょう。ただ、すり鉢には溝があるため、細かくした後は刷毛などで溝に入った遺骨をかき出す必要があります。
遺骨をパウダー状にする作業は家庭用のミルやミキサーでも代用ができます。ただ、調理用のものなので、作業をした後は調理用に使用するのは抵抗があると思います。
遺骨を細かくする方法として、密閉できる袋を数枚重ねて上から叩く方法もあります。比較的やわらかい遺骨であれば、綿棒や指などで押しつぶすことができます。固い遺骨をたたく場合は力を入れ過ぎて袋が破けないように注意しましょう。
3. 粉骨した遺骨の保管方法
粉骨ができたら湿気が入らないように遺骨は真空パックの袋に入れます。すぐに散骨する場合は、水分が付着していない容器に遺骨を入れて保管しておきます。
その場合も、カビなどの繁殖を防ぐため高温多湿な場所は避けて、風通しの良い場所に保管します。リビングなら直射日光は避け、窓から少し離れた場所に置くようにしましょう。
自宅に遺骨を置く場合は見た目にも配慮が必要です。人によっては遺骨を「怖い」と感じる方もいるでしょう。そのため、最近ではインテリアになじむような様々な形の手元供養専用の骨壺が売られていますので、いろいろと探してみるといいでしょう。
4. 粉骨を業者に頼む場合の注意点と費用の相場
粉骨を自分で行うのは作業自体に手間がかかる以外にも、心理的な負担もかかります。その上、きれいなパウダー状にするのは難しいため、専門の業者に依頼するという選択肢もあります。費用は骨壺のサイズや持ち込みか郵送かでも変わってきますが、一般的な相場は、持ち込みの場合は8,000円~20,000円程度、郵送の場合は15,000円~30,000円程度です。遺骨の状態によっては遺骨を乾燥させる費用が発生し、オプションで5,000円~15,000円程度です。また立ち合いの場合も費用が発生することがあり、10,000円前後が相場のようです。
しかしながら大切な故人の遺骨を任せるため、信頼できる業者に依頼したいものです。
そこで、業者を選ぶ際は以下のような点を注意して選ぶといいでしょう。
粉骨の実績が数多くあること
粉骨に関するきちんとした知識があり、経験と実績のある業者を選ぶようにしましょう。いいかげんな業者だと、例えば喉仏は分けて欲しいとお願いしても、別の骨を渡される可能性もあります。もしインターネットなどで口コミがあれば確認するといいでしょう。
対応がしっかりしていて親身になってくれる
依頼者の気持ちを理解し、丁寧な対応をしてくれる業者であれば、大切な遺骨を心を込めて粉骨してくれるでしょう。
料金が明確になっている
後から追加料金が取られないためにも、最初から金額が明記されていると安心です。粉骨するためには、異物を除去したり粉骨した遺骨を真空パックの袋に入れたりと様々な作業が発生します。それらを明確に記された料金体系になっているか確認しましょう
大切な遺骨を自分で手間をかけて粉骨することは、大切な供養の一つであり、それによってしっかり最後までお見送りをするという意味で心の区切りなるかもしれません。それ同時に、遺骨を手元供養する場合は、最終的な遺骨の埋葬方法は事前に決めておくようにしましょう。自分が亡くなった後に家族が困ってしまったり、継承者がいない場合は無縁仏になってしまうこともあるので、事前によく考えておくことが大切です。